目次・概要
審査に合格した状況
└申請日から合格までの期間
└申請までの近況
└申請時の環境と実施内容
└ブログを始めた時期、これまでの経緯と流れ
振り返り
└合格できた理由、出来なかった理由
└ブログ記事の内容で心がけたこと
まとめ
└ブログの現況
└審査合格後の主観的な推測と憶測
※この記事の内容はGoogle AdSense収益化の申請に関してのヒントとしてあくまでも自己責任で参考程度にして下さい。この記事を元に申請し不利益が生じましても当ブログは一切の責任を負いかねますので予めご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。

審査に合格した状況
申請日から合格までの期間
所要2日(実質1日)2025年5月19日18:00頃に申請、2025月5月20日8:55に合格メールを受信。
申請までの近況
しばらく放置していたので5月初旬にブログを開くと403 Forbidden エラーを確認し、ログインも不可能だった。
googleアナティリスクをみると申請前の2025年1月26日に異常を検知されていた。
Xserverのメールサポートを受けて5月13日に復旧してから3記事を追加して37記事にして申請。
申請時の環境と実施内容
サーバー:Xserverスタンダード
CMS:WordPress
テーマ:コクーン
主なプラグイン:Contact Form 7、Site Kit by google、WP Multibyte Patch その他
広告掲載:A8ネットの広告を掲載している。
投稿記事数:37記事
ブログを始めた時期、これまでの経緯と流れ
開始した時期:2023年7月
投稿期間:2023年7月~2025年5月
未投稿期間:2024年3月~2025年4月(約1年1ヵ月未投稿、ほぼ休眠放置)
異常発生:アナティリスクの履歴で2025年1月26日に異常検知、ユーザーがドロップとなる。5月初旬に403 Forbidden エラー発生して気付き、すぐに対応し復旧。その後審査を受けて合格。
アドセンス収益化審査申請回数:4回目で合格
クリック数:異常発生前2025年1月が3.5k
申請の履歴
2023年7月:1回目審査申請7記事→不合格
2023年9月:2回目審査申請21記事→不合格
2024年4月:3回目審査申請34記事→不合格
2025年5月:4回目審査申請37記事→合格
振り返り
合格できた理由、出来なかった理由
合格できた理由
推測ですが「有用性の低い」に関するのプログラムポリシーを克服できたのかもしれません。大変申しわけありません。詳細はわかりません。結果が解答というこで、真相は adsense の中です。
出来なかった理由
Google AdSenseからの不合格メールが「広告を掲載する準備がまだ整っていない」、「広告を掲載できるようにするには、いくつかの問題を解決する必要がある」との内容でした(一部抜粋引用)。つまり、プログラムポリシーに準拠できていなかったということになります。
ブログ記事の内容で心がけたこと。
google アドセンス承認通過の可能性を高めるにはと公式動画内で紹介されていることがあります。(Google AdSense公式YouTubeチャンネル「サイトが承認されるには」音声より一部翻訳・引用)
- 「広告コードを正しく配置する」
- 「リーチ可能なサイトにすること」
- 「プログラムポリシーに準拠していること」
「プログラムポリシーに準拠していること」については更に
- 「有用性の低いコンテンツではない」
- 「複製されたコンテンツではない」
- 「サイトナビゲーション(操作性があること)」
google adsense のプログラム、コンテンツポリシーに準拠すること。
と紹介されています。(※出典:Google AdSense公式YouTube「サイトが承認されるには?」(URL)より一部引用・翻訳)
google adsense のプログラム、コンテンツポリシーに準拠することを意識する。
有用性の高いこと
- 当ブログの記事を見て分からなかったことが解決できる。
- なるべく最初のところを端折らない。しかし、くどくならないようにする。
- 不合格になる理由は「有用性が低い」とadsenseから判断された事を忘れない。
- 役にたった、為になった、世のため、人のためを目指す。
複製をしない
- 他人の記事のコピペはしない。
- 同じ事象の記事を見倣う事は大事だが自分で検証、体験して自分の観点、言葉で記事をかく。
操作性が良い
- 記事をカテゴリーかタグで仕分けする。ページ内リンクをつける。
- ヘッダーメニューにカテゴリーメニューを入れる
- フッターメニューにプロフィール、問い合わせ等の固定ページを入れる
再現性があること
- 当ブログを見た人が同じ手順で実施したときに同じことが出来る。
- 投稿済みの記事を日にちが経ってから読み返し、状況が変わり再現出来なくなっている、分かりくければ書き直す。
視認性を良くすること
- 直感的な読みやすさを目指す。
- 記事の内容、項目を多くしすぎない。
- 書いてるうちに関連項目をあれもこれもとなってくるがあきらめも必要。
- 詰め詰め文、長文にせず、適度に句読点、空白、改行と空白行をつかう。
- なるべく箇条書きのような端的な文面をめざす。
- なるべく主語を述語の順で書き、文章の流れを同じようにする。結論をしっかり書く。
- 太字、マーカーを適度につかう。
誹謗中傷はしない。虚偽は書かない。間違いに気付けば書き直す。
タイトルと記事の内容に乖離が無いようにする。
ブログの認知度
- ASPの登録と広告掲載のお願いのメールが来たので当ブログがネット上で多少の認知されているのではないかと推測。
他社の広告掲載について
- 広告を掲載して審査しても大丈夫だったこと
- ネットの情報で広告を掲載すると審査が通らない論もあったが1回目はアマゾンリンクを載せていた。2回目と3回目は広告やリンクは掲載しなかった。4回目は掲載したが大丈夫だった。
申請時の記事の必要な実績(推測)
- ある程度の記事数 内容にもよるが10記事~30記事 (当方37記事投稿)
- ある程度の閲覧数やクリック数 (異常検知する前月は3.5kクリック)
まとめ
ブログの現況
始める前は色々を調べてブログの書き方やジャンルをどうするとか迷いはありましたが、現在の特化的雑記なブログと自己判断しています。
最初の頃はWebデザインスクールの内容の記事が主でしたが、スクールの受講修了後、現在はグラフィックデザインアプリの使用手順や日常発生するブログ製作に係わる内容となっています。
審査合格後の主観的な推測と憶測
ここからはあくまでも主観的な推測と憶測のひとりごとです。
それなりに読んでいただければ幸いです。
先述にもありますが、アドセンスブログにおいて必要なこととして
- 有用性あり
- 複製しない
- サイトナビゲーションあり(操作性)
そうなると有用性があるかどうか?これが一番重要で困惑するところです。
有用性とは「役にたつ」、「実用的」、「効果的」であり困ったときに「目的が達成」できればそれで意味を成すのではないでしょうか。結局のところ要るか?要らないか?ということです。
- テーマに主体性があり専門的であること。
- 主観的な視点でもよいので何か独自性を見つける。
- 見やすいように文章、画像の配置する。
- サイト内で迷子にならないようリンクボタンなどの視認性、操作性をよくする
- 簡単な内容にして再現しやすくする
- 問題を解決できる
これが実現できれば有用性にあてはまるのではないでしょうか。
有用性の意味は検索すれば答えがでますが、アドセンスの審査に合格するのが目的で、それをどう言語化、具現化するかに対しては審査結果でしか解答がないで困ったもんなんです。
GoogleAdsenceのyoutube「サイトが承認されるには?」にアドセンスプログラムポリシー、コンテンツポリシーの紹介動画があります。これを見て自分なりの解釈をするもの1つの方法です。
自分自身でどんなブログ?って問うたときに「〇〇なブログです。」と答えられる内容に達していれば良い気がします。自分で言えればブログの主体性が人にも伝わるでしょう。
有用性は見てもらえて役にたつ、為になれば大丈夫ではないでしょうか。世のため人のためです。
見てもらえないとスタートラインに立てないだろうというのもあります。
記事数に関しては、主体性、専門性のあり(範囲にもよる)方向性の見える良質な10~30記事ぐらいは最低必要かと考えられます。
合格しない理由が量と予想される場合は、例えば1つの内容を判断するのに10記事が目安だったとするならば主体性、専門性の範囲を広げ3カテゴリーからはじめたら単純に出揃うまでに30記事は必要となります。
当ブログの場合は大まかにはデザイン関連ですが、webデザイン、グラフィック等で分かれておりアプリに関しては1つではないのでそれなりの記事数は必要だったのかもしれません。
結果的にwebデザインかグラフィックのどちらかに限定して内容をより掘り下げて専門的にしていれば違った結果になったかもしれませんが、それは「たられば論」となります。
当初は掘り下げられる専門的な知識もまだまだ足りなかったので、出揃うまで時間はかかるが自分のレベルでの検証、体験を元に記事にしました。
ブログはブログの数だけ違う内容であり独自性があるので、まるっぽ複製はこれどっかで見たぞと分かってしまいます。
自分と同じ観点を持つ方で見てくれる人はいるかもしれませんが、独自性が有りすぎで他人に伝わらない内容ではそれもよろしくないかもしれません。カリスマ性があれば大丈夫かも。。
あとは自問自答を繰り返すのみです。
また何か思いついたら書き足したします。それでは。

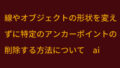
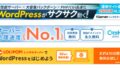
コメント